
愛犬の体のケアは定期的に行うことがとても大切です。
特に体の小さいチワワは、細かな歯の磨き残しや耳のお手入れ忘れが、将来の病気に直結することもあり得ます。
この記事では愛犬のチワワにストレスなく長生きしてもらうための正しい歯磨き、耳掃除、爪切りのやり方についてまとめています。
チワワの歯磨きはどうする?

生後4週間頃
毎日がベスト
歯磨きを始める時期は、生後4週間頃がベストです。この時期の子犬は社会性を学ぶ期間とされていて、将来歯磨きを嫌がらずに覚えてもらう最適な時期だからです。
歯磨きのタイミングは食後30分以内か就寝前に行い、できるだけ毎日、最低でも週2回を目安に行うことをおすすめします。
歯磨きを始めたばかりだと慣れるのにも一苦労です。最初は2~3日に一回のペースで行ってみましょう。
必要なグッズ
犬用歯ブラシ
ガーゼ
歯磨きガム
犬の歯磨きに必要なグッズは、「犬用ブラシ」「ガーゼ」「歯磨きガム」などです。
犬用ブラシ
犬用の歯ブラシです。
ブラシが硬すぎると口内を傷つけたり痛い思いをさせてしまうことがあるので、柔らかいものを選ぶようにします。また、ヘッドが大きすぎると歯茎にぶつかってしまうので、あまり大きくないサイズを選びます。
また歯ブラシを噛まれてボロボロになることも多いので、ストックを何本用意しておくと良いですよ。
歯磨きをするうえで、犬用ブラシは一番綺麗に磨くことができ、歯周病の予防にもなります。
ガーゼ
指にガーゼを巻いて、歯垢を取り除く方法です。
ガーゼを巻きつけや指で歯を直接拭うことができるので初心者の方でもやりやすいですよ。破れやすい素材でないか、抜け落ち防止の工夫がされているかをチェックします。
強くこすりすぎると歯肉に刺激が加わり痛みを伴う場合があるため、優しく拭き取るようにしましょう。
歯磨きガム
グリニーズやオーラベット、ペットキッス、などから販売されている犬用歯磨きガムです。
無添加や口臭対策の成分が含まれているものなど様々なものが販売されています。素材によって硬さが違うので、愛犬の体型やアレルギーの有無などをふまえて最適なものを選んであげてください。
歯磨きガムだけでは完全に汚れを落とすことができないため、追加でガーゼで汚れを落としたり、歯磨きにも挑戦するようにしましょう。
正しい歯磨きの方法
口元を触られることは犬にとってストレスになるので、スムーズに終わらせることを心がけます。
まずは口に触られることに慣れさせましょう。おやつなどをうまく利用することでだんだん慣れてくれます。
口に触ることができるようになったら少しずつ歯磨きを行います。
・触りやすい前歯から優しく磨く
・奥歯の外側まで磨き終わったら裏側も磨く
注意点
歯磨き粉は人間用のものではなく犬用のものであれば使うことができます。
ニオイや味にこだわっているものや、口臭予防に役立つ成分が配合されているものもあるので、犬の嗜好に合わせて選べば歯磨きタイムがお気に入りの時間になるかもしれません。
人間用の歯磨き粉をおすすめしない理由は、犬には有害とされている「キシリトール」が含まれているからです。
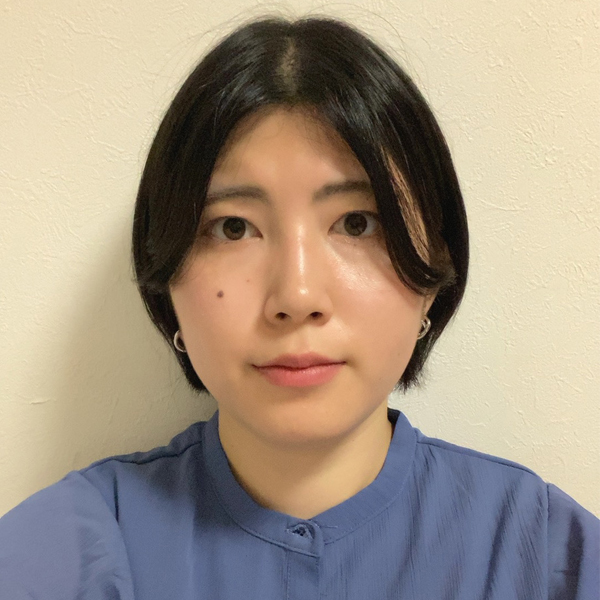
愛玩動物看護師 渡邉鈴子さん
キシリトールは犬にとって有害です。犬が摂取すると低血糖を起こします。絶対に人間用の歯磨き粉は使用しないでください。
また歯磨きでチワワの口内が出血してしまうこともあります。原因は「力を入れすぎている」ことがほとんどなので、毛先の柔らかいブラシを使って歯の表面を撫でる程度の力を意識して下さい。
一度歯磨きで痛い思いをしてしまうと歯磨きを嫌がるようになってしまいかねないので、力加減には細心の注意が必要となります。
チワワの爪切りはどうする?

2週間に1回
人間の爪と同じようにチワワの爪も伸び続けるので、定期的に爪を切らなければなりません。
放置していると、引っかかって根元から折れたり肉球に刺さったり(弧を描くように伸びるため)することもあります。肉球が地面に着きづらくなるので、滑って怪我をする原因にもなります。
必要なグッズ
犬用の爪切り
ヤスリ
爪切りは、人間用ではなく犬用のものを用意します。
やり方
犬の爪は根元から先端まで同じ太さの円柱状になっているので、角度を変えながら角を取るように少しずつ切っていきます。
大根の面取りをするように爪先を丸く仕上げると、爪が当たっても痛くないのでおすすめです。
注意点
爪は伸びると、中の神経と血管も一緒に伸びます。
切りすぎて血が出てしまったときは、綺麗なコットンを1分程度押し当てれば出血は止まります。もし心配な場合は止血剤を用意しておくと安心ですよ。
チワワの耳掃除はどうする?

耳の中が汚れていたら
耳掃除は、定期的に耳をチェックして汚れていたタイミングで行います。
「急に耳垢が増えた」「ベトベトしている」「酸っぱいにおいがする」場合などは外耳炎になっている可能性が高いので、動物病院で診察を受けることをおすすめします。
必要なグッズ
イヤークリーナー
イヤーローション
イヤークリーナーやイヤーローションを使うと耳掃除しやすいです。
やり方
普段の耳掃除であれば、イヤークリーナーをコットンに付けて耳の内側の汚れを拭き取るだけで十分です。
注意点
耳の中があまりにも汚れている、においがキツイ場合は、念入りな耳掃除が必要です。
1:愛犬の耳道内にイヤークリーナーを数滴注いで漏れないように注意しながら耳の根元をマッサージします。
2:チワワが首を振れば、イヤークリーナーと耳垢が一緒に出てくるので綺麗に拭き取る
きちんと掃除できるか心配な場合は、獣医師さんなどにお願いすることをおすすめします。
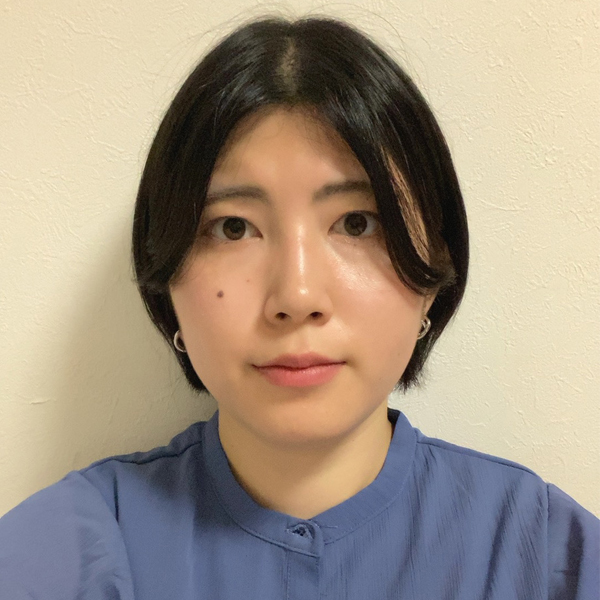
愛玩動物看護師 渡邉鈴子さん
耳掃除では人用の綿棒は使用しないようにしましょう。犬の耳の皮膚は人と異なり薄い構造をしています。人用の綿棒では刺激が強すぎて耳の皮膚を傷つける恐れがあります。必ずコットンやガーゼなど柔らかい素材のものを使用して優しく拭き取ってください。
難しい場合はプロを頼ろう!

自分自身で愛情を持ってケアしてあげたいという気持ちもわかりますが、痛い思いや辛い思いはさせたくはないですよね。
難かしい場合は無理をせず、プロに頼んでみてくださいね。




