
犬は人間同様、性別によりかかりやすい病気が異なり、高齢のメス犬がかかりやすい病気として「子宮蓄膿症」があげられます。出産経験がなく、避妊手術をしていない中高齢のメス犬によくみられる病気です。
この記事では子宮蓄膿症が起こる原因や発症したときの症状、手術による治療法などについてまとめました。
目次
犬の子宮蓄膿症とは?原因は?

子宮蓄膿症とは、大腸菌などの細菌が子宮に侵入して炎症を引き起こし、子宮内に膿が溜まってしまう病気です。
高齢になり、免疫力が低下したときに多くみられます。若いときでも発情期後の黄体期に入ったときは受精のために精子を受け入れようと免疫機能が低下しているので、子宮蓄膿症を発症しやすくなっています。
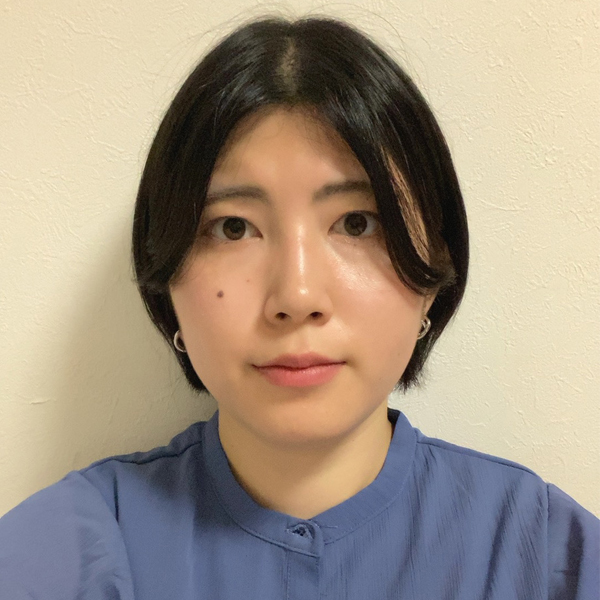
愛玩動物看護師 渡邉鈴子さん
免疫機能が落ちると、普段感染しにくい細菌にも感染しやすい状態になります。
犬の子宮蓄膿症の初期症状は?
子宮蓄膿症を発症すると、初期症状として以下のようなものがみられます。
●元気がなくなる
●食欲が低下する
●発熱、嘔吐、下痢
●多飲多尿
●陰部から膿がでる
●腹部膨満
この状態からさらに進行すると、子宮が破裂して腹膜炎を引き起こすだけでなく、細菌から出される毒素によって腎不全や敗血症性ショック、播種性血管内凝固症候群(DIC)、多臓器不全など重い病気を発症する危険があります。
初期症状の段階ではただの体調不良に見え、重症化してから気づくケースも多い病気です。元気がないと感じたら動物病院に相談しておくと安心ですよ。
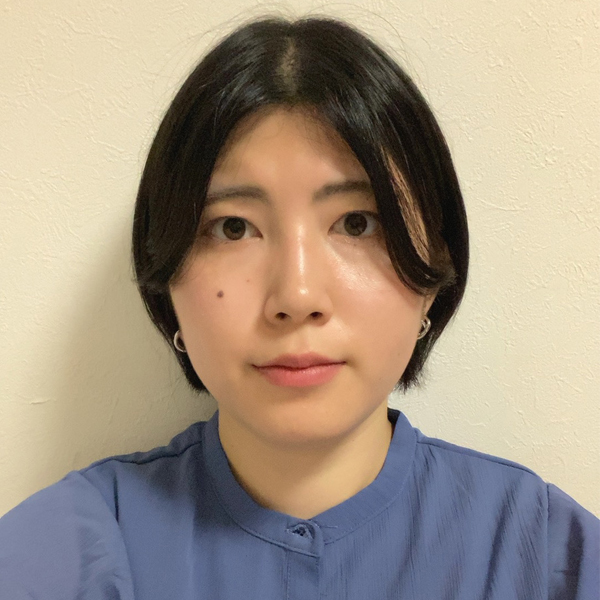
愛玩動物看護師 渡邉鈴子さん
子宮蓄膿症には開放性と閉鎖性の2つあり、閉鎖性の場合、陰部から膿が出ません。それに飼い主が気づくことができず、子宮が破裂して、腹膜炎を引き起こすこともあります。妊娠していないのにお腹が張っているなと感じたら子宮蓄膿症を疑いましょう。
犬の子宮蓄膿症は手術で治療する?

子宮蓄膿症を発症しているかどうかは、レントゲン検査とエコー検査で子宮を確認して判断します。細菌に感染すると白血球数などの数値が高まるので、一緒に血液検査も実施します。
子宮蓄膿症であることが判明したら、すぐに手術で膿の溜まった子宮を摘出する必要があります。内科療法のみで治療することもできますが、それだけで完治することは難しく、再発する危険性が高くなります。
初期段階であれば手術をすることで完治することが可能です。
適切に治療を行えば予後は良好ですが、多臓器不全になってしまった場合は死亡する確率が高いです。
犬の子宮蓄膿症の手術費用はどれくらい?
手術の費用は病院や地域によって大きく差はありますが、50,000円以上はかかると考えておきましょう。
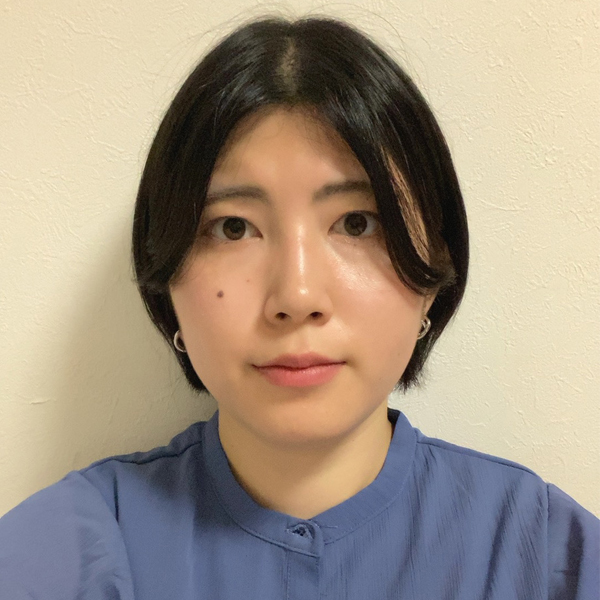
愛玩動物看護師 渡邉鈴子さん
あらかじめ、ペット保険に入っていることで手術費用を抑えることができます。うまく活用しましょう。
犬の子宮蓄膿症の術後に気をつけることは?
術後7日~10日ほどは、食欲がない、出血がある、震える、傷口を舐める、散歩を嫌がる、などが見られることもあります。
少しずつ体調は回復していきますが、もし体調が戻らないときは一度獣医さんに相談してみてください。
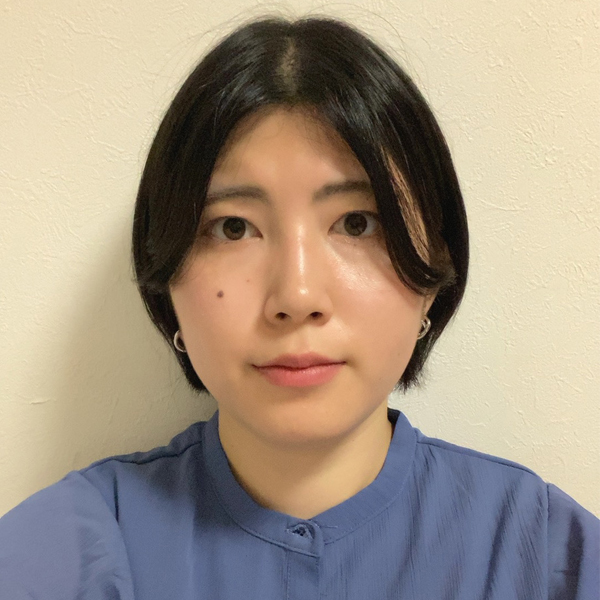
愛玩動物看護師 渡邉鈴子さん
術後は痛みによるストレスがとてもかかる状況にあります。安静にすることは前提として、お家での生活環境の工夫を行いましょう。静かな場所で室温や湿度など適度な環境で休ませることが重要です。同居動物がいる場合は、回復をさせるために別室での飼育を行うか距離が取れるようにしましょう。散歩などの運動は傷口の治癒状況にもよりますので、獣医さんと相談のうえ、行いましょう。
犬の子宮蓄膿症を対策するには?
子宮蓄膿症を対策するには、避妊手術で子宮を摘出する方法があります。子どもを産ませないのであれば、早めに避妊手術をしておくと万が一の危険を避けることができます。
避妊手術を行う場合、生後3〜4ヶ月頃が最適な時期といわれています。
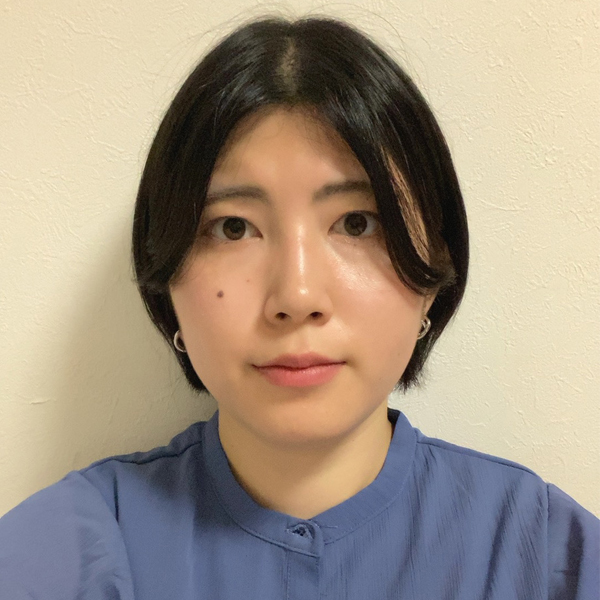
愛玩動物看護師 渡邉鈴子さん
避妊手術は子宮蓄膿症だけではなく乳腺腫瘍や卵巣腫瘍の病気の予防にもなります。わんちゃんを飼育し始めて適齢期が来たら行うことをおすすめします。
犬の子宮蓄膿症は早期発見が大切

子宮蓄膿症は、放置していると重症化する危険な病気ですが、早期発見して対処すれば完治できます。
普段から愛犬の様子をみてあげて、少しでも体調が悪そうだと感じたときにはすぐに動物病院に連れて行ってあげてくださいね。
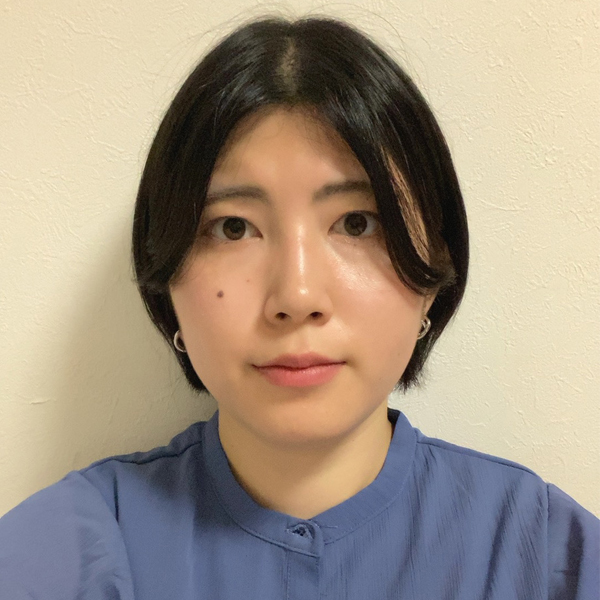
愛玩動物看護師 渡邉鈴子さん
実際に膿が出ないタイプの子宮蓄膿症になったわんちゃんは重症になってから飼い主さんが気づくことがあります。膿が出ているから動物病院に行かなきゃという判断ではなく、普段からスキンシップを取ってしっかり日々の様子を見てあげることが大切です。




