
愛犬が急に痙攣を起こしたら、びっくりしてしまいますよね。
痙攣は命にも関わる病気なので、少しでも知っておくといざというときに役立ちます。
この記事では犬の痙攣に関する、症状・原因・対処法についてまとめました。
目次
犬の痙攣、どんな症状?

全身をこわばらせて震える
痙攣を起こすと、数秒~数分間全身をこわばらせて震えます。1回だけで終わることもあれば、何度か繰り返すこともあります。
体が固まったようになり、手足をピンと伸ばし、全身をピクピクと細かく震わせます。手足だけを震わせたり顔面だけを震わせたりといった部分的な痙攣もあります。
痙攣時に「気を失う」「よだれが出る」「嘔吐する」「おしっこを漏らす」などの症状を併発することも。
犬が痙攣を起こす原因は?

てんかん
犬クリプトコッカス症
ジステンパーウイルス感染症
門脈シャフト
中毒
1:てんかん
犬の痙攣の原因として最もみられるのが、てんかんであり特発性てんかんのことを指します。
特発性てんかんは全身どこにも異常がなくてもてんかん発作が起きてしまう病気です。遺伝的な要因が強く疑われる病気でもあります。
脳の中に痙攣の原因となる炎症や腫瘍のような病変があるてんかんを症候性てんかんと呼びます。
2:犬クリプトコッカス症
犬クリプトコッカス症の原因は、クリプトコッカスと呼ばれる真菌です。
クリプトコッカスが中枢神経に達することで神経に異常をきたし、神経の不具合から痙攣します。
他にも呼吸器系に肉芽腫を作るためやっかいな病気です。
クリプトコッカスは人獣共通感染症でもあるため、注意が必要です。
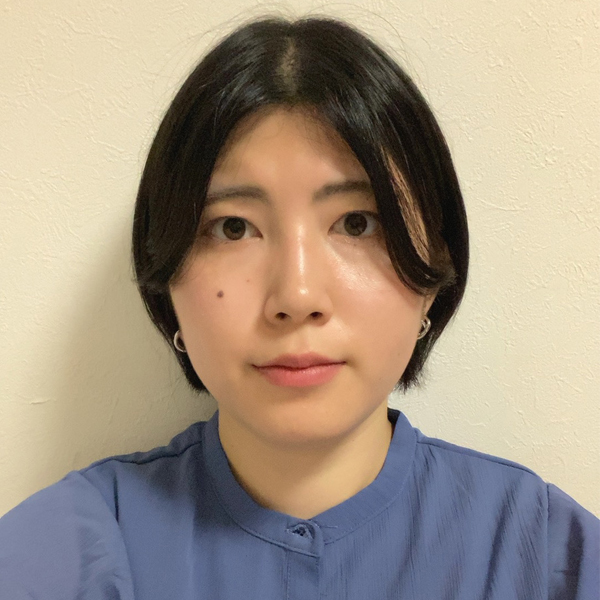
愛玩動物看護師 渡邉鈴子さん
人獣共通感染症とは、動物と人に共通して感染する病気のことを言います。
3:ジステンパーウイルス感染症
ジステンパーウイルス感染症の原因は、ジステンパーウイルスです。
ウィルスが中枢神経系にまで達することで、神経に異変が起き痙攣が起こります。
一歳未満の幼若犬がかかりやすい病気です。
4:門脈シャント
門脈シャントの発症の原因に肝性脳炎があります。
肝性脳炎になると脳に障害がおきるため、痙攣や歩行困難などの症状が現れます。
門脈シャントには先天性のものと後天性のものがあります。
5:中毒
中毒症状の1つに痙攣があります。
「玉ねぎ」「チョコレート」「キシリトール」「除草剤」「殺虫剤」などの犬が口にすると危険なものを食べてしまうことで中毒を起こし、痙攣を起こします。
痙攣を起こしやすい犬種がいる?

痙攣を発症しやすい特定の犬はいませんが、「てんかん」や「先天性の門脈シャント」を起こしやすい犬種は注意が必要です。
てんかんの発症率は、全ての犬種を合わせても0.6~0.75%といわれており、1~3歳のころに発症しやすいとされています。
てんかんを発症しやすい犬種
アメリカンコッカースパニエル・イングリッシュコッカースパニエル・ゴールデンレトリバー・コリー・ジャーマンシェパード・シェットランドシープドッグ・シベリアンハスキー・ダックスフント・ビーグル・プードル・ボーダーコリーなどです。
突発性てんかんを発症しやすい犬種
アイリッシュウルフハウンド・ベルジアンタービュレン・ボーダーテリア・プチバセグリフォンヴァンデアン・フィニッシュスピッツ・スピノーネイタリアーノ・ラブラドールレトリバーなどです。
先天性の門脈シャントを発症しやすい犬種
ヨークシャーテリア・マルチーズ・ミニチュアシュナウザー・アイリッシュウルフハウンド・オールドイングリッシュシープドッグなどです。
愛犬が痙攣を発症してしまった場合の対処は?

てんかん
てんかんは、発作を起こしているときの症状を詳しく獣医さんに伝えると治療がスムーズに進みます。
愛犬が発作を起こしたら飼い主さんはできるだけ冷静に発作の様子を観察するようにしてください。冷静でいられないようなときはスマホなどの録画機能で発作の様子を撮影しておくことをおすすめします。
また、発作を起こしている間は、愛犬もパニックになっている場合があります。愛犬が発作中にぶつかってケガをしそうなものは離れた場所に移動させるなどして安全を確保してください。
発作が治まったのを確認できたら、すぐに病院へ行き診察を受けてくださいね。
症候性てんかんの場合、ほかの病気が関わっていることもあるためその治療ができれば治すことも可能です。
犬クリプトコッカス症
アムホテリシンB・ケトコナゾールなどの抗真菌剤投与と並行して、鼻炎や皮膚炎、目や中枢神経の異常などの症状に対する治療を行います。
ジステンパーウイルス感染症
ジステンパーウイルス感染症には対処法がありませんが、速やかに病院へ連れていき治療を受けてください。致死率がとても高い病気です。
発症した段階で免疫力が低下しているので、抗生物質を投与して二次感染を起こさないことが大切です。
けいれんのほかに、目やにや鼻水、発熱などの風邪のような症状を起こします。
門脈シャント
輸液・投薬・利尿剤・結石の除去など、症状に合わせた治療を行います。基礎疾患があれば併せて治療します。
中毒
中毒症状の場合、食べたものによっては命を落とす危険性があります。
愛犬が危険なものを口にしたと分かったら、すぐに病院へ連れていき処置を受けてください。
痙攣を起こした場合どんな検査が必要?

問診
神経学的検査
血液検査
検査1:問診
動物病院に到着した時には発作が治まっていることが多いため、まずは発作の様子や発作前の様子を問診します。
検査2:神経学的検査
犬の痙攣はてんかんが原因であることが多いため、この検査で特発性てんかんと症候性てんかんのどちらであるかを検査します。症候性であれば原因がはっきりとわかり的確な治療を受けることが可能です。
特発性てんかんの場合は、抗てんかん薬による治療が行われます。
検査3:血液検査
血液を採取して、原因が「てんかん」か「てんかん以外」なのかを見極めます。
この検査では、低血糖・低カルシウム血症・ウィルス感染などがわかります。
愛犬が痙攣を起こしたときは焦らず病院へ

愛犬が痙攣を起こしている場合、まずは原因を突き止めるのが最優先です。気になる体調の変化などは記憶しておき、通院時に獣医師に伝えましょう。
不調が見当たらずてんかんだと診断されたときは、抗てんかん薬を使い発作の頻度を減らすことを目標に治療を行います。
てんかんによる発作・痙攣は対策できず、見守るしかありません。もしも長時間続いたり頻発したりする場合は、すぐに病院へ連れて行きましょう。




