最近、愛犬にマイクロチップを入れるという方が増えてきています。
マイクロチップはどういったものであるかわからない方も多いのではないでしょうか。犬を飼ううえでどのように役立つものなのかも疑問に思いますよね。
この記事では、犬の体内に入れるマイクロチップについてまとめました。
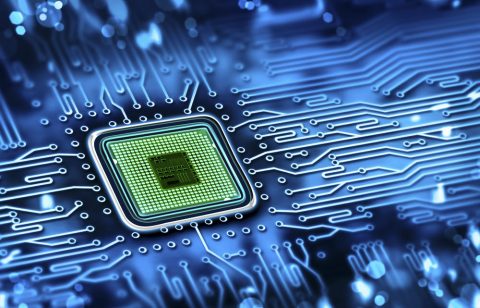
犬のマイクロチップ、なんのために使うの?

マイクロチップは、犬を明確に識別するために使います。
日本にはペットに関する法律で「動物の所有者は自分が所有者であることを明らかにすること」が義務になっています。「ペットの命の保証」と「飼い主の責任の明確化」がその理由です。
室内飼いの犬であっても外へ出ることがありますし、大きな災害で飼い主と犬が離ればなれになってしまうこともあります。ペットの盗難事件などが増えていることも心配ですよね。
これらのとき、マイクロチップを用いた個体識別がペットと飼い主を繋いでくれるのです。
個体識別にはどんな方法がある?

マイクロチップによる個体識別方法とともに、他の4つの個体識別方法を確認してみてください。
マイクロチップ
世界的に主流となってきている個体識別方法です。
犬だけ限らず、猫、馬、鳥、爬虫類、魚など多くの動物に装着することができ、別のものに付け替えることはほぼ不可能です。デメリットは外から見て装着していることを判断できず、マイクロチップリーダーという機械が必要になることです。
費用も高めで、獣医師に装着をお願いする必要があります。
首輪
最も一般的で簡単、安価にできる個体識別方法です。
ノラ犬ではないことがひと目でわかります。素材も革・布・金属など様々でファッション性もあり、動物の名前や飼い主の情報を書き込んでおくことができますよ。
デメリットは取り外すのも簡単なことです。また、劣化してしまうと書き込んだ情報を読み取るのが難しくなることも注意するべきポイントです。
名札
首輪につけることが一般的な個体識別方法です。
動物の名前や飼い主の情報を書き込むことができ、簡単に装着できます。こちらも首輪同様取り外しが簡単で、劣化すると情報を読みとることが難しくなります。
タトゥ
犬や猫、ウサギなどでよく行われている個体識別方法です。
一度入れるとほとんど消えることがありません。海外では入れ墨をして個体識別することが義務とされている国もあります。
デメリットは動物に入れ墨を入れる技術者が少ないことと、動物に負担が掛かることです。耳など皮膚が露出している場所に施すものなので入れる場所が限られ、入れることができる情報は多くありません。
耳標
牛の個体識別方法としてよく知られています。
耳に付ける名札のようなものです。中型~大型の動物に適した方法で、安価でつけることができます。ICタグが付いているものもありますよ。
デメリットは犬の場合激しく動き、外れて落とすことがあることです。破損する可能性もあり表示できる情報は少ないです。
犬のマイクロチップはどんなもの?

マイクロチップは長さが8~12mm、直径が2mmほどで、インジェクターという注射器のようなものを使って動物の皮下に埋め込みます。
犬や猫の場合、首や肩のあたりに装着するのが一般的です。マイクロチップリーダーという機械を近づけると、世界に一つしかない番号が表示されます。
日本では15桁の番号が主流で、国、動物、販売元などの意味があります。番号と飼い主の情報をデーターベースに登録しておくと、ペットが迷子になってもマイクロチップリーダーで番号を読みとり、データーベースから飼い主を探し出すことができるのです。
犬のマイクロチップ、装着は病院?

マイクロチップは動物病院で装着できます。
費用はマイクロチップ代と装着技術料を合わせて5,000〜10,000円程です。動物病院でマイクロチップを装着すると「IDデータ登録申込書」という書類がもらえます。
この書類にはマイクロチップ番号、装着した日、施術した獣医師、動物情報、飼い主の情報などが載っています。
この情報をもとにデーターベースに登録するための手続き(書類の送付と手数料1,000円の支払い)を行うと、マイクロチップの番号と飼い主の情報がデーターベースに登録されます。
マイクロチップは個体識別がしやすい
ペットが迷子になってもマイクロチップを動物愛護センターや動物病院で読みとることができればデーターベースにアクセスし、飼い主を探し出すことができます。
また、海外旅行のときにはマイクロチップの埋め込みが必須となります。ヨーロッパには90%以上のペットがマイクロチップを装着している国もあります。
もしものときのために、マイクロチップの埋め込みを検討してみてくださいね。




