ハリネズミはペットとして人気が出るとともに、生態についても関心が高まっています。
ヨーロッパに住んでいるハリネズミは昔から「幸運のシンボル」として愛されていたため詳しい情報が多くありますが、アフリカに住んでいるハリネズミに関しては情報が少ないのが現状です。
この記事では、日本でペットとして飼われているハリネズミ(ヨツユビハリネズミ)の生態と特徴についてまとめました。
この記事でまとめたこと
ハリネズミの生態・習性とは

ハリネズミは、夜行性の動物です。
アフリカ大陸の赤道付近やサバンナと呼ばれる熱帯の草原に住んでおり、乾いた岩場や草が茂った場所を好んで生活していますよ。
単独行動
ハリネズミは野生下において、群れを作ることはしません。
単独でいることを好むので、ペットとして飼育する場合は1頭ずつケージに入れるようにしてください。オスとメスの組み合わせでも、繁殖期以外に一緒のケージに入れるとケンカしてしまいますよ。
複数飼育はケガやストレスにも繋がりますし、ストレスが続くと病気になることもあるので気をつけてくださいね。
夜行性
ハリネズミは繊細でストレスを感じやすい動物で、飼いはじめた頃は、環境の変化などでかなりストレスを感じています。飼ったばかりでかわいくて、いつでも手に取って触りたくなりますが、しばらくは日中のスキンシップを控えましょう。
ハリネズミは夜行性の動物ですから、飼いはじめはハリネズミ本来の生活リズムに合わせてあげてくださいね。一緒に生活をしていけば、徐々に生活リズムが同じになってくることもありますよ。
飼育環境の温度は一定に
ハリネズミは寒くなると冬眠、暑くなると夏眠します。この冬眠と夏眠はペットとして飼っているハリネズミにとっては大きな体の負担となり、最悪の場合、死んでしまうこともあります。
ハリネズミを飼う環境の温度調整は非常に難しいのです。ハリネズミを飼う時の適性温度は25度~29度で、一年中この気温を保つ必要があります。夏と冬は特に気をつけてくださいね。
泡つけ(アンティング・香油塗り)
ハリネズミは未知のニオイを嗅ぐと、舐めたりかじったりして口の中に入れて泡状のだ液と混ぜ、長い舌で背中の針に塗る習性があります。
なぜ、見知らぬもののニオイを針に塗るのかについては分かっていませんが、「驚いた時の反応」や「カモフラージュ」ではないかと考えられていますよ。
飼育下においては、慣れない環境で見られる事が多いですね。病気が原因の行動ではありませんが、何度も繰り返すようであれば飼育環境の見直しをおすすめします。
ハリネズミの身体的特徴とは
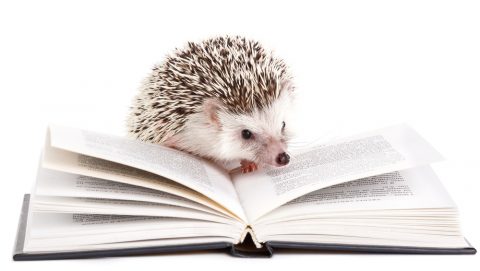
ハリネズミ(ヨツユビハリネズミ)は名前の由来通り、4本指の後ろ足が特徴的です。
ハリネズミのカラーバリエーションと特徴
ハリネズミの体色
- スタンダード(ソルト&ペッパー)
- シナモン
- アプリコット
- シニコット
- ブラックアイドシニコット
- ブラウン
- アルビノ
- パイド
スタンダード(ソルト&ペッパー)

「スタンダード(ソルトアンドペッパー)」は、白い針に黒いバンド・マスク(顔)と鼻は黒・黒目です。
シナモン

「シナモン」は、白い針に明るい茶色のバンド・マスクと鼻は茶色がかったピンク・黒目です。
アプリコット

「アプリコット」は、白い針に薄い茶色のバンド・白っぽいマスク・ピンクの鼻・赤目です。
シニコット

「シニコット」は、シナモンとアプリコットの中間の色です。白い針にやや薄い茶色のバンド・マスクと鼻はピンクです。
ブラックアイドシニコット

「ブラックアイドシニコット」は黒目、「ルビーアイドシニコット」は赤目ですよ。
ブラウン

「ブラウン」は、白い針に茶色のバンド・くすんだピンクのマスク・茶色い鼻・黒目です。目のまわりに茶色いリングがありますよ。
アルビノ

「アルビノ」は、白い針・マスクと鼻はピンク・赤目です。
パイド

「パイド(ピント)」は不規則なぶち模様や上半身と下半身が異なるカラーになるなど、同じパターンにならないのが特徴ですね。
ハリネズミの食事
野生のハリネズミは、「昆虫」「ミミズ」「カタツムリ」「カエル」「ハ虫類」「小さい鳥」「小さい哺乳類」「果物」「木の実や種」「キノコ」などを食べています。
飼育下では「ハリネズミ専用フード」をメインに、オヤツとして「生きたミルワーム(昆虫の幼虫)」「生きたコオロギ」を与えますよ。
専用フード以外を与えるときには、野生の食性に合った獣肉を主原料にしているフードであり、脂質が10~20%であるかの確認も忘れないでくださいね。
ハリネズミの知能
ハリネズミの脳は、哺乳類の中では小さいとされていますが、記憶力は優れているので学習することはできます。また、嗅覚と聴力が良いのでニオイや声で飼い主さんを覚えることもできますよ。根気強く教えれば、トイレを覚えさせることも可能です。
ハリネズミの針
ハリネズミの針は5000本以上あるとされます。
この針は敵から身を守るための役割を果たすもので、高い場所から転落したときにクッションの役目にもなりますよ。
警戒している時は体を丸めて針を立て、「シュー」や「プシュー」と鳴きながら飛び跳ねて威嚇します。少し驚いている時は、おでこの針のみを立てます。安心している時は針は寝ているので、撫でることもできますよ。
ハリネズミの鳴き声
ハリネズミは普段は鳴かない動物です。鳴いたとしても、大きな声は出しませんよ。
警戒・威嚇している時は、鼻から「シュー」「シュッ」「プシュー」と息を吐き出します。「ふしゅられた」「ふしゅふしゅされた」と飼い主さんが言っている場合は、威嚇されたことを意味していますよ。
探検している時や餌を探している時は「フンフン」と鼻を鳴らします。
そのほか、繁殖期が近づいたオスやハリネズミの赤ちゃんは、「ピー」と小鳥のように鳴きますよ。
ハリネズミの感覚
視覚
視覚は良くありません。
背中の針がクッションになるとはいえ、視力が悪いので段差がわかりにくく、高いところから落ちることもあるので注意が必要ですよ。
聴覚
聴覚は優れています。
聞こえる音域が広いので、人間には聞こえない音を聞くこともできますよ。慣れてくると、飼い主さんの声を聞き分けることもできます。
嗅覚
嗅覚も優れていますよ。
ただ、人工的なニオイはストレスになってしまうので、ニオイのある石鹸や洗剤などを使うとハリネズミは混乱してなかなか飼い主さんを覚えてくれません。
触角
ひげは触覚器官の役割を果たしています。
周囲の情報を知るために付いているので、むやみやたらに切らないようにしてくださいね。
ハリネズミの便
餌によっても替わりますが、健康な便は茶色で細長い形をしています。
飼育下では、環境が変わった場合などに緑色の便が3~5日ほど見られることもありますが、元気があって食欲もあれば心配ありませんよ。
ハリネズミをよく観察してみよう!

ハリネズミに関する情報はまだまだ多いとは言えません。
愛情をこめて世話をし、定期的に観察することが病気やケガの早期発見につながりますよ。ハリネズミとの生活を少しでも長く楽しむためにも普段からよく観察してあげてくださいね。
ハリネズミの特徴と飼い方のポイントと、飼育グッズまとめはこちらの記事で紹介しています。






