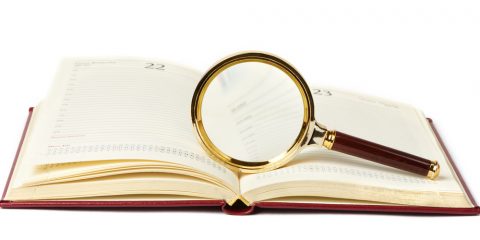アオマダラウミヘビは、コブラ科エラブウミヘビ属に分類される毒ヘビです。
世界を代表するウミヘビの一種ですが、日本近海では沖縄海域でしか見ることが出来ない珍しい品種ですよ。
この記事では、アオマダラウミヘビの種類、野生下での餌や天敵をまとめました。ぜひ参考にしてくださいね。
この記事でまとめたこと
アオマダラウミヘビの体色の種類は?

| 体色 | 青~青灰色地に黒い縞模様 |
|---|---|
| 外見の特徴 | 頭頂部と目の後ろが黒い |
| 鮮やかな黄色~黄白色になっている口と喉 | |
| 腹面を覆う鱗(腹板)が幅広い |
青~青灰色地に黒い縞模様
アオマダラウミヘビの体色は、青~青灰色(青みがかった灰色)地に黒帯が入っています。
黒帯の幅は地の青よりやや狭い個体が多いですが、個体によっては同じくらいの幅をしている個体もいますよ。
英語名である「Yellow lipped sea snake」は口元が淡い黄色になっていることに由来しています。顔面の色味は個体差がありますが、黄色いとアオマダラウミヘビの場合がほとんどですね。
年齢と共に黒くなる?
アオマダラウミヘビは、老熟すると黒褐色(黒っぽい茶色)に黒い縞模様という黒色個体に変化します。
徐々に体の青味や顔面の黄色味があせていき、全身が黒味の強い色彩になっていきますよ。 ただ、アオマダラウミヘビはエラブ亜種の中でも色彩の鮮やかさがあまり失われない品種とされています。
ヒロオウミヘビとの見分け方は?
ヒロオウミヘビとは、黒帯の幅で見分けることが出来ますよ。
ヒロオウミヘビの黒帯は青帯と同じ位の幅か、幅が広くなっています。また、全体的なシルエットがアオマダラウミヘビと比べると若干太めです。
アオマダラウミヘビの餌、野生下では何を食べている?

野生下での餌
- 魚類
- 長い魚
アオマダラウミヘビの食性は動物食です。
主に浅い海に生息する「ベラ」「スズメダイ」「ギンポ」などの小魚や、「アナゴ」「ウツボ」などの長い魚を採餌しますよ。
夜の海で活動することが多いですが、昼には岩礁に上がることもあるのでネズミなどの小型哺乳類も餌になりえます。
アオマダラウミヘビの天敵はいる?

天敵
- 存在しない
アオマダラウミヘビには天敵は存在しません。
極めて毒性が強い神経毒を持っているため、ほかの動物に捕食されないのかもしれませんね。
「ウミヘビ」と「エラブウミヘビ」

ウミヘビは「ウミヘビ亜種」と「エラブウミヘビ亜種」の2系統に分類されます。
日本近海で見られるウミヘビ亜種は「イイジマウミヘビ」「クロガシラウミヘビ」など9種、エラブ亜種は「エブラウミヘビ」「ヒロオウミヘビ」「アオマダラウミヘビ」の3種です。
多くのウミヘビは体内で孵化させ海中で幼蛇を産みますが、エラブ亜種は陸上で産卵するという大きな違いがありますよ。